教育に関わる人であれば,一度は抱えたことがある悩みだと思います。
子どものやる気を引き出すのってなかなか難しいですよね。
そんな悩みを解決するために,
私もこれまでに数多くの教育書を読み,いくつかの方法を試してきました。
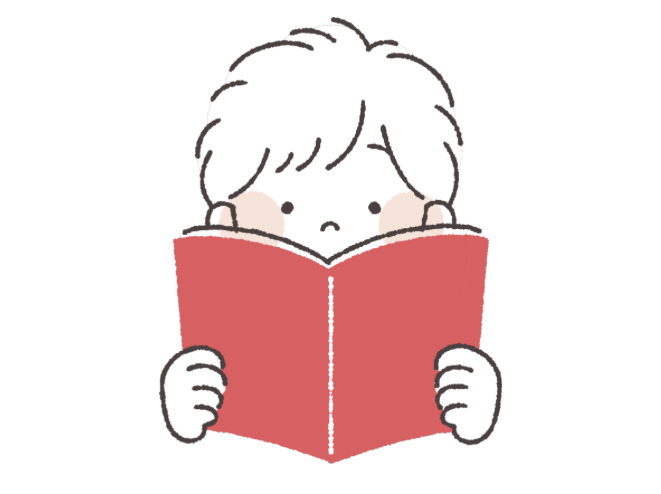
そこで今回は,年間300冊の本を読む教育者の視点から
科学的な研究をもとに,
やる気を引き出す方法を解説しながら,厳選した本3冊を紹介します!
目次
1.子どもの勉強のやる気を高めたい時に読みたい3冊
①「やる気」を科学的に分析してわかった小学校の子が勉強にハマる方法
1冊目に紹介する本は,中学受験専門塾伸学会の菊池洋匡氏,秦一生氏の共著
「やる気」を科学的に分析してわかった小学生の子が勉強にハマる方法です。
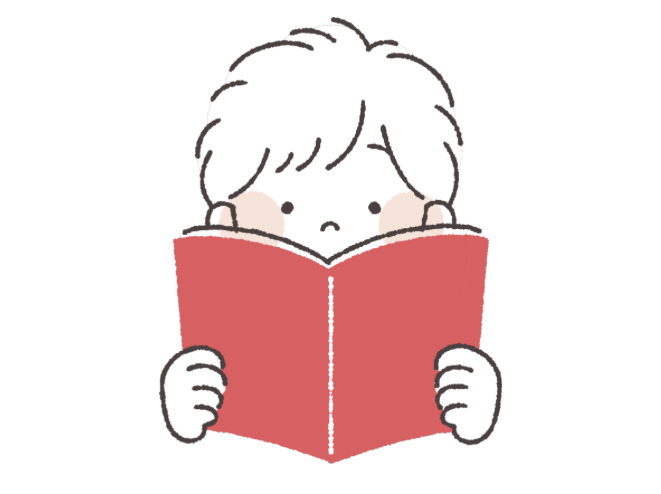
著者は保護者の方がもつ共通の悩み
「子どもが勉強を嫌がる」を解決するためにARCSモデルという学習意欲を高めるモデルを採用しました。絵もたくさん使われていて,比較的読みやすい1冊です。
菊池氏は,仕事も勉強を楽しむためには「技術」が必要だと述べています。
このARCSモデルは,Google社でも採用されている技術です。
ARCSモデルは、アメリカの教育工学者 J・M・ケラー が提唱した,学習者のやる気(モチベーション)を高めるためのモデル です。
①Attention(注意)
②Relevance(関連性)
③Confidence(自信)
④Satisfaction(満足感)の
4つの要素から成り立っています。
※本書では,日本人に対して分かりやすくするめに「Reason(理由)」で紹介されています。
ARCSモデルの4つの要素
① Attention(注意)
→ 「おもしろそう!」と興味を引く
例:クイズ形式にする,自分育成ゲームにする
② Relevance(関連性)Reason(理由)
→ 「やりがいがある」と感じさせる
例:身近な話題と結びつける,学ぶ理由を伝える,目標を子どもに設定させる
③Confidence(自信)
→ 「これならできそう!」と思わせる
例:小さな成功体験を積ませる,適切なレベルの課題を用意する
④Satisfaction(満足感)
→ 「やってよかった!」と実感させる
例:努力を認める,勉強が役立ったと感じる機会を作る
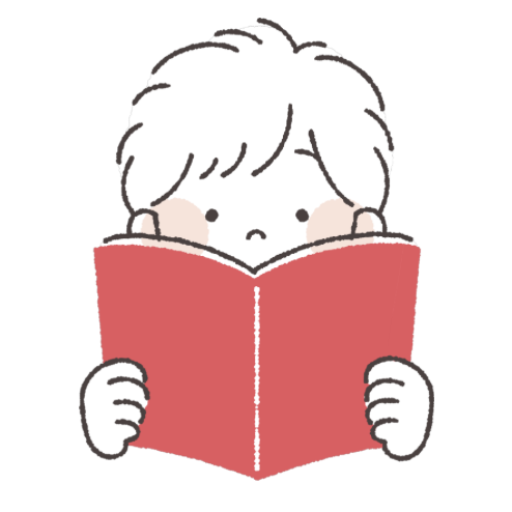
著者によれば,いきなり4つの要素を満たす必要はないそうです。
1つでも2つでもARCSの要素を入れることができると,子どもの学習意欲が高まっていきます。
本書では,具体的な事例をもとに,小学生が勉強にハマる方法を紹介されています。「やってはいけない5つのご褒美のあげ方」など大人がやりがちな失敗例もあげられています。
②THE LEARNING GAME 自分の頭で考え、学ぶ楽しさ、挑戦する喜びを教えよう
2冊目に紹介するのは,教育起業家であり,イーロン・マスクが作った学校(アド・アストラ)でも勤務する,アナ・ロレーナ・ファブレガの著書
The Learning Game 自分の頭で考え、学ぶ楽しさ、挑戦する喜びを教えようです。
子供達に学ぶことへの愛情を植え付けることは,私たちが与えることのできる,最も価値のある贈り物である。
アナ・ロレーナ・ファブレガ著 「The Learning Game」より
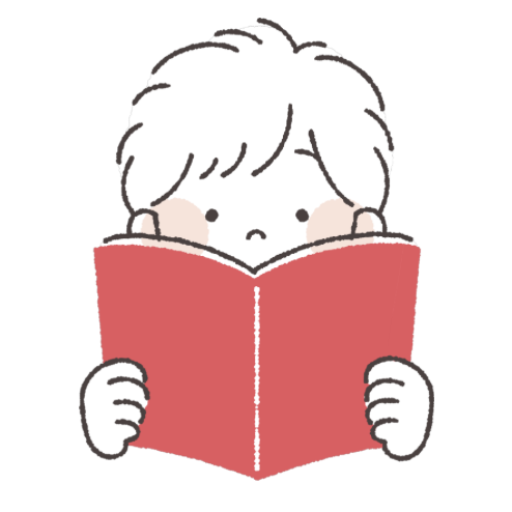
アナ・ローレン・ファブレガは,子供達に学びの愛情を植え付けるための方法としてゲームに着目をしています。

確かに!子どもたちはゲームをしている時は,楽しみながら集中して取り組んでいます!
The Learning Gameの中で著者は,「学びのゲーム化」のヒントになる手法を多数紹介しています。近年注目されている「ゲーミフィケーション」に通じるものがあります。
ゲーミフィケーションとは「ゲームの要素やメカニズムを非ゲームの領域に応用し,
対象者の行動や態度にポジティブな変化を促す手法」です。(岸本2023)
簡単に言うとゲームの要素を違う場面に取り入れよう!ってことですね。
ゲーミフィケーションには以下の 6 つの要素が含まれます。
①能動的な参加
②達成可能な目標設定
③賞賛を演出
④即時のフィードバック設計
⑤成長の可視化
⑥独自性の歓迎
岸本好弘(2023)「ゲーミフィケーション 6 要素と対応する心理学用語」
『日本デジタルゲーム学会 2023 年 夏季研究発表大会 予稿集』一般社団法人日本ゲーミフィケーション協会, p. 173
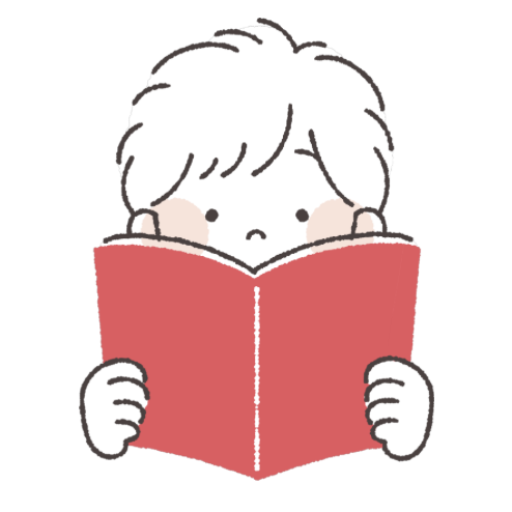
宿題をただ出したり,させたりするのではなくて,
この6要素のどれかを取り入れてゲームっぽくすると効果的です。
例えば⑤成長の可視化するために,ポイントシステムを導入したり,取り組みに対して③賞賛を演出する場を設けるといいかもしれませんね!
③学習設計マニュアル: 「おとな」になるためのインストラクショナルデザイン
3冊目に紹介するのは,教育工学者である鈴木克明氏と学習環境デザインが専門の美馬のゆりの共著 学習設計マニュアル:「おとな」になるためのインストラクショナルデザインです。
本書の目的は「読者が自分の学びをデザインできるようになること」です。
様々な理論が出てくるので,興味を持ったものについて詳しく読むことをおすすめします。
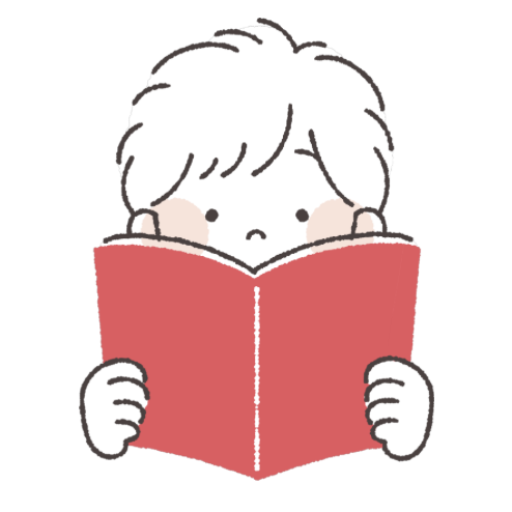
本書で特徴的なのは「学ぶ側の視点」と「教える側の視点」で様々な理論について整理されていることです。本書の第3部では, 認知的徒弟制(にんちてきとていせい)という理論について言及されています。
認知的徒弟制(にんちてきとていせい)は親方と弟子の間で古くから行われてきた,職業訓練のプロセスを学習的な観点から理論化したものです。ブラウンは以下の4つの段階に整理しました。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ①モデリング | ・お手本を示す 熟練者が課題の解き方や思考プロセスを示す。 |
| ② コーチング | ・支援しながら取り組ませる 学習者が実際に課題に取り組み、教師が適切なフィードバックを行う。 |
| ③ スキャフォールディング | ・徐々に支援を減らす 学習者の成長に応じて、支援を少しずつ減らしていく。学習者が実行困難な場合に一時的に支援する。(足場かけ) |
| ④ フェーディング | ・自立して学ぶ 最終的に支援(足場)を完全に外し、学習者が自分の力で問題解決できるようにする。 |
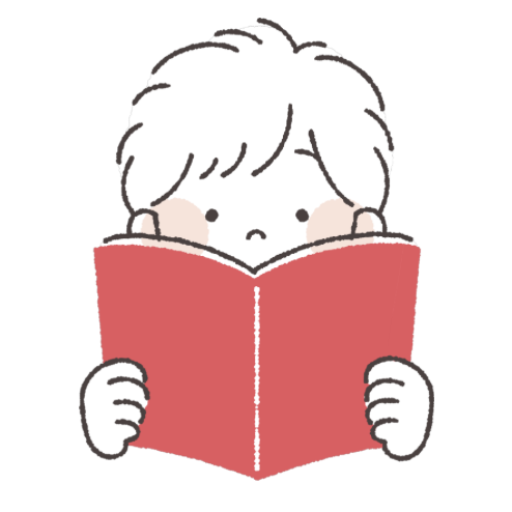
子どもにとって,簡単すぎても難しすぎても「やる気」はでてきません。
どの段階に子どもがいるかを適切に把握して,必要な関わり方をしていくことが大切になりますね!
2.まとめ
今回は「子どもの勉強のやる気を高めるには?」をテーマに3冊の本を紹介しました。
どの本も理論に基づいており説得力があります。
実態に合わせて,色々な方法を組み合わせてみるといいかもしれません。
- 「やる気」を科学的に分析してわかった小学校の子が勉強にハマる方法
- THE LEARNING GAME 自分の頭で考え、学ぶ楽しさ、挑戦する喜びを教えよう
- 学習設計マニュアル: 「おとな」になるためのインストラクショナルデザイン
Hataori Libraryでは,絵本や教育書をはじめとした様々な もの・こと・ひとを紹介していきます。公式LINEで更新通知をしますので,下記ボタンからぜひご登録をよろしくお願いします。
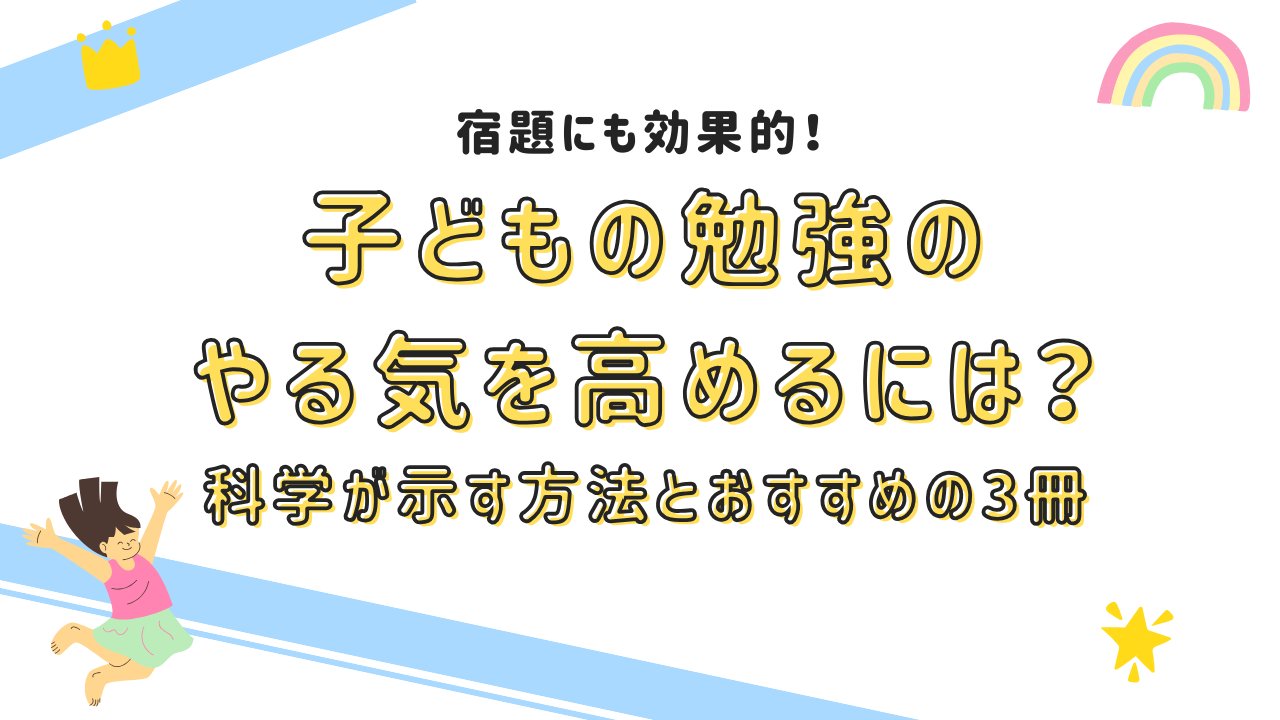


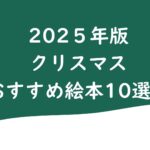
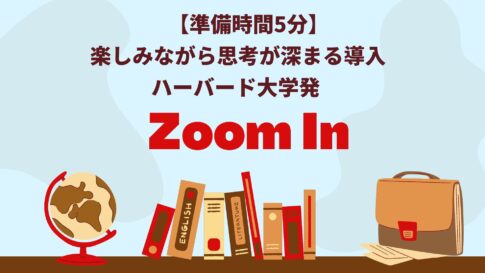
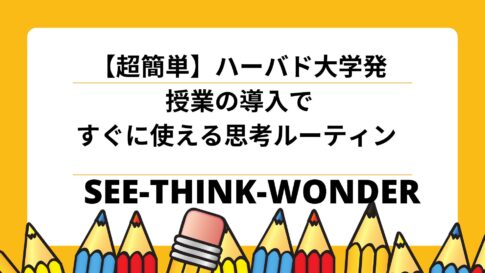
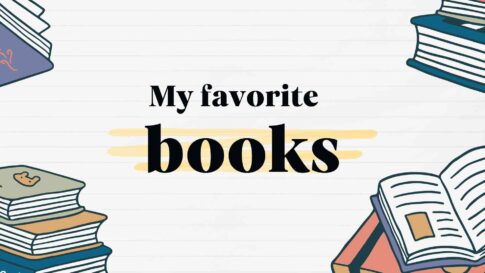


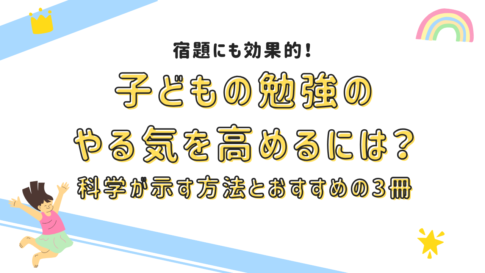
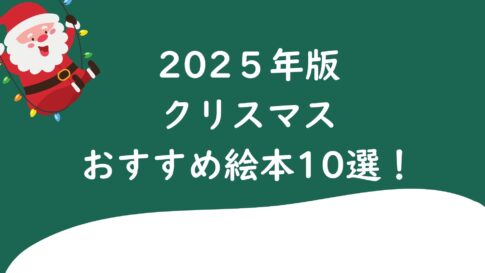
・うちの子,どうして勉強にやる気が出ないんだろう?
・クラスの子どもたちの勉強へのモチベーションを高めたい。